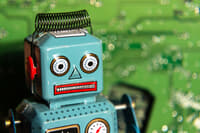- HOME
- コラム
- Edge of Europe
- イギリスでもじわり漂う大麻容認の空気
イギリスでもじわり漂う大麻容認の空気
1930年代アメリカの禁酒法のよう
一方で、合法化に賛同する論調も目にする。大麻を合法化することで、状況を改善させられるというものだ。認可を受けた店だけが18歳以上の客だけに限定して販売できるよう、また、起こり得る有害な結果をきちんと警告表示することができるよう、法律によって規制すべきだ、と。大麻に課税すれば、政府の収入源にできるだけでなく、大麻価格をあまり気軽に買う気が起きないレベルに引き上げることもできる(今のところ、大麻を吸うのはアルコールを飲むのよりかなり安い。それこそ、若者が大麻を好む理由の1つだ)。
そのうえ、合法化で犯罪組織の収入源も奪われるし、もしかしたら一部の大麻使用者がよりハードなドラッグに手を出すのを抑止することができるかもしれない。その理論はつまり、現状では大麻を買ううちに、大麻だけでなくコカインやヘロインなどの「よりハードな」ドラッグを売る密売人に何度も接触するようになるということ。密売人はこう言って盛んに勧めてくる。「大麻が気に入ったなら、これもきっと気に入るよ......ほら、1回タダで試してみろよ......」
大麻解禁の声は、若者や「ヒッピー系」からばかり上がっていると思われがちだが、今年になって強引にこの議論を持ち出したのは、英保守党の元党首ウィリアム・ヘイグだ。彼は、これまでのドラッグ論争は「徹底的に取り返しのつかないほど負け」だったと主張。今やあらゆる政党から多くの政治家が大麻合法化を呼び掛けており、中には「医療用に限って」賛成という議員もいる(重度のてんかんや多発性硬化症のような症状に効果があるようだ)。
事実上、イギリスの大麻合法化論争は、1930年代アメリカの禁酒法のようなものだ。当然許されるべきだと多くの人々が考えているものを国が禁止しようとし、人々は法を無視してまでそれを手に入れるようになり、結果としてその状況が犯罪組織を潤わせる。
それでも僕は、政府が大麻合法化に踏み込むとはどうしても思えない。何らかの危険性があり違法だったものに対して、単純に「降伏して」合法化する、などということには、「平均的なイギリス人」なら拒絶反応を示すだろうから。
僕には解決策が分からないし、合法化に賛成も反対もしていない。今回このブログで取り上げたのは、これが現代イギリスの悩ましい難題であり、「嗅覚」のある人なら誰しも気付いている問題だからだ。
【お知らせ】ニューズウィーク日本版メルマガのご登録を!
気になる北朝鮮問題の動向から英国ロイヤルファミリーの話題まで、世界の動きを
ウイークデーの朝にお届けします。
ご登録(無料)はこちらから=>>
みんなやっていることだけど...庶民の味方の政治家、庶民的な不正で窮地 2024.04.26
そこにない幻の匂いを感じる「異嗅症」を知ってる? 2024.04.25
価値は疑わしくコストは膨大...偉大なるリニア計画って必要なの? 2024.04.17
英キャサリン妃の癌公表で「妬み」も感じてしまった理由 2024.03.28
死に体政権は悪あがき政策に走る 2024.03.13
イギリスはすっかり「刃物社会」になった......あまりに多発するナイフでの死傷事件 2024.03.09