Huawei一色に染まった中国メディア──創設者が語った本音
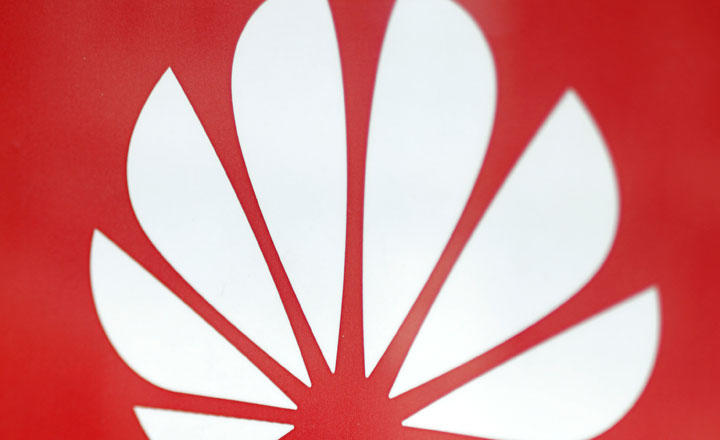
中国を燃え上がらせているHuawei Edgar Su-REUTERS
Huawei創業者の任正非CEOは、5月21日、中国メディアの取材に応じ、150分間にわたって本音を語った。中国のメディアが一斉に報道しHuawei一色に染まった。そこから見えるものは?
初めての現象
中国のメディアが、ここまでHuawei(華為技術。以下「華為」)の情報を「全開」の形で報道するのは、初めてのことだ。
これまでは、昨年、華為の孟晩舟CFOが拘束された時でさえ、中央テレビ局CCTVは多くの時間を費やさず、外交部報道官は海外向けに激しく抗議していたが、中国の国内向けには控え目だった。ましてや昨年末に開催された改革開放40周年記念大会で表彰された100人のリストにさえ華為の任正非氏は入ってなかったくらいだから(参照:2018年12月30日付けコラム「Huawei総裁はなぜ100人リストから排除されたのか?」)、華為のことを大々的に報道することなどあり得なかった。
ところが、CCTVの解説によれば、120日ほど前から任正非氏がメディアに顔を出すようになり、5月21日の午前中には中国のほぼ全てのメディアの取材を受け、同日午後にはCCTVの単独取材にも応じた。これら全ての過程をCCTVが一日中報道し続け、他のメディアもそれに倣った。CCTVの最上位にいる名物司会者・白岩松氏が久々に登場し熱気に燃えて力強く報道する様は、圧巻とさえ映った。
まるで中国のメディアが華為一色に染まった形だ。
CCTVは任正非氏を「民族の英雄」とさえ言った。世界に対して「革命」を起こさんばかりの勢いだ。
抗日戦争時に生まれた、現在の中国の国歌の中にあるフレーズ「中華民族は最も危険な時期に達した」を華為の現状に当てはめていることから、国家全体として「人民戦」を闘い抜こうという意思が読み取れる。
それならなぜ、100人リストから外したのか、そして中国のAI巨大戦略における中国政府指定の先端企業5社(BATIS)から、なぜその最高レベルの半導体チップを持っている華為を外したのか(参照:2019年2月12日付けコラム「中国のAI巨大戦略と米中対立――中国政府指名5大企業の怪」)。
そもそも、この報道ぶりの「激変」自体から、米中貿易戦争あるいは米中ハイテク戦争における中国政府の基本姿勢が見えてくる。
今ごろになってとは思うが、中国はようやく、華為を「中国の顔」として使い、「米中貿易摩擦の根幹は、米中ハイテク覇権競争にあり」、「アメリカが、中国のハイテクがアメリカを追い抜こうとしていることに恐怖を抱いているからだ」というメッセージを世界に発信しようとしていることが見えてくる。
記者と任正非氏とのQ&A
では任正非氏は、あのぼくとつとした口調で何を語ったのか。
その全記録をご紹介したいが、日本語に翻訳したら5万字を超えるだろうから、「これは」と思われる注目点を抜き出す以外にない。




















