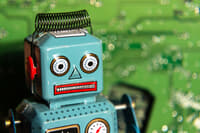緊急事態宣言と医療崩壊の日中比較:日本を救う道はまだあるのか?
国務院(中国人民政府)は1月23日に武漢封鎖を命じた瞬間から、24時間以内に、すなわち1月24日までに「突発的公共衛生事件第一級対応機能」に対応せよという指示を出している。
この「突発的公共衛生事件緊急対応条例」というのはSARSが蔓延した2003年5月9日に発布されており、突発的な疫病の流行によって、瞬時に中国全土に実施を強制することが可能な緊急条例である。疫病の程度によって「一級」から「四級」まで区分されている。今回は最高レベルの「一級」発令となった。
これに即応して、中国全土の地方人民政府が、その地区の感染度合いによって対応の仕方を決めていく。
各地方人民政府がどのように実行しているかは中央に上げられ、国務院および中共中央が確認し監視する。
その具体的な内容や緊急対応の状況などは、たとえばこちらや、こちらなどをご覧になれば、雰囲気がお分かりいただけるだろう。
まるで戦時下の空襲警報が鳴ったような対応の仕方で、時々刻々進捗状況が報告されネットで公開された。中央テレビ局CCTVでも分刻みで緊急対応状況が報道され、まさに「いま津波が押し寄せています!」という緊迫感が中国全土を覆っていたのを窺がわせた。
それに比べた安倍政権の対応の「ゆったりさ」。
「躊躇なく」を声高に叫んではいるが、実施は優柔不断の「躊躇」の連続ではないのか。
医療崩壊阻止に対する日中比較
先述のコラム<中国はなぜコロナ大拡散から抜け出せたのか?>で述べたように、鍾南山は1月19日に武漢視察をした瞬間から新型コロナウイルスの危険性を察知し、20日に習近平に重要指示を出させるところに漕ぎ着けたが、同時に医療崩壊を来たすことを予期して方艙(ほうそう)医院を突貫工事で建築することを建議し実行させている。
その結果、6万床の重症患者対応も可能なベッドと4.3万人の医療従事者を武漢に集めることに成功している。
一方では2018年3月に設立した行政組織である「中華人民共和国 国家衛生健康委員会」も医療緊急対応体制を強化している。
片や、わが日本はどうなのか。
実は昨年(2019年)10月28日、安倍首相は「病院再編と過剰なベッド数の削減など指示」している。